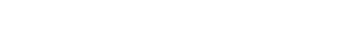「共生」の倫理
1年前期の「人間共生論」は本学に入学したすべての1年生が履修する特別科目です。学生は倫理観や他者を理解する姿勢を身につけます。
大学病院での早期体験学習
1年後期には埼玉医科大学総合医療センター検査部を見学しながら臨床検査技師の仕事の説明を受けます。現場を知ることにより、2年次から始まる専門科目が実際の検査にどのように結びつくかをイメージできるようになります。
マナー講座と模擬患者実習
3年次の臨地実習前には、社会人としての素養を学ぶためのマナー講座と、患者さんに対する態度やコミュニケーションスキルを習得する模擬患者実習を実施しています。
臨地実習
3年後期には、大学病院や地域の中核をなす総合病院で臨地実習を行います。学生は少人数に分かれて、10月から1月まで指定された病院の検査部の各部門を回りながら病院でしか得られないことを学んでいきます。
【大学生活密着レポート第2弾】臨床検査学科篇(実習中の起床時間は午前5時30分!)
卒業研究
4年前期には7つある研究室のいずれかに所属して、卒業研究を行います。ここでは、単なる知識ではなく、それをもとにした問題解決能力を高めていきます。卒業研究発表会に向けてプレゼンテーション能力も高めます。
チーム医療論I
4年次には学部横断的な授業としてチーム医療論Ⅰが設けられています。この授業では、さまざまな視点をもつ多くの職種が連携をとることによって、患者さんへのよりよい治療が実現することを学んでいきます。
国家試験対策
4年次には、国家試験に直結する多くの講義があり、自然に国家試験対策ができる学習環境になります。定期的に模擬試験があり、学習方法・ペースについて学生一人一人がアドバイスを受けます。4年生のアドバイザーは、卒業研究の所属研究室の指導教員が担当しており、親身になって年間を通じてのサポートにあたっています。
- ●総合臨床検査学
- 臨床検査技師として働くために学ぶべき内容は、非常に多く、多岐にわたります。1年生から様々な科目を履修して、次々と学ぶ内容を積み重ねていきますが、国家試験受験前には、それまでに学んだ内容をまとめ、知識のつながりを意識しなければなりません。4年次の「総合臨床検査学」では、国家試験に関わる科目を復習しながら、総合的な学力を身につけることを目的にしています。後期になると、2~3週間ごとに国家試験の模擬的な試験を受け、自分の苦手分野を把握し、教員からのサポートを受けながら国家試験合格を目指します。
- ●研究室でのサポート体制
- 卒業研究期間は、4年生が研究室の教員と最も身近に接します。この間に、配属研究室単位で、教員が学生一人一人の学習計画と達成状況を把握し、指導と助言を行っています。同じ研究室の大学院生から個別指導を受ける学習サポート制度を利用する4年生もいます。
- ●研修生制度
- 大学を卒業しても、残念ながら臨床検査技師国家試験に合格できなかった場合、資格取得のために、さらに学力を向上させる必要があります。研修生制度は、そのような卒業生をサポートするためにあります。研修生になると、在学生と同様に図書館などを利用でき、すべての授業で学び直したり、学内で行われる模擬試験を受験することができます。
学習面に関するサポート体制
大学の授業は高校までの授業スタイルから大きく変わります。学習内容が多く、授業後の復習など自ら学習する習慣を確立することが重要となります。授業担当教員やグループ別のアドバイザー教員のフォロー以外にも、正課外教育として学習サポート制度とグループ学習を導入しています。
学習サポート制度
先輩である大学院生に希望する科目の疑問点を教えてもらうことができます。学内で行う家庭教師のような制度で、学部生は誰でも無料で利用できます。
グループ学習
本学科ではグループアドバイサー制を採用しており、1学年を6人~7人ずつのグループにわけ、1~3年が同じグループに所属します。4年生は研究室の教員のグループに所属します。
同じグループのメンバーと一緒に勉強し、授業の重要なポイントを確認したり、疑問点を共有し、お互いに教え合ったりします。多学年合同のグループ活動もあり、1~4年生が集う交流会などを通じて、まずは同じグループの先輩と仲良くなれると思います。授業でわからないことがあっても気軽に先輩に相談できるようになります。また、グループの先輩からグループ以外の先輩を紹介してもらうなど、ネットワークを広げることができ、「国家資格取得」という同じ目標を共有する仲間をたくさん作ることができます。
就職・進学
大学を卒業して、臨床検査技師国家試験に合格した学生は全員が就職しています。
また、臨床検査学科では毎年2月に各分野で活躍している卒業生を招いて、就職先を考える機会として進路指導ガイダンスを行っています。どの学年の学生も参加可能で、卒業生の輝いている様子を間近で見られることから毎回好評を得ています。進路指導ガイダンスは定期的に開催しているため、先輩からの経験談や就職に関する情報をたくさん得ることができます。