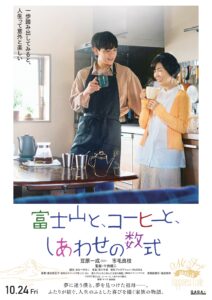
今回は前回の続きの文章を紹介します。
思い出すことなど 島田和幸
P.73 万里の道も一歩から 勉学や人生に似る富士登山 より抜粋
母は、昭和17年の夏、自らこの「五」を試みるため、有志生徒十人ばかりと男性教員一名、それに私(当時小学校5年)のお供で富士登山に挑みました。もともと足のきわめて弱い人でしたし、私も頑健ではありませんでしたから、これはきつかったのです。戦時下のガソリン統制で、既に富士吉田から登山口までのバスもなく、電車で朝早く富士吉田駅に降りたあとは、もうただ、つえを頼りに歩くのみです。途中の山小屋で、コップ一杯十銭の水は飲めましたが、戦前からの名残である森永ミルクキャラメル、チョコレート、カルピス、などというホーロー製の看板をうらめしく横目で眺めながら、ひたすら登ります。キャラメルはおろか、ジュースすら買えない時代です。六合目までマイカーでさっと登れる現代では、想像も難いでしょう。
この登山の結果を簡単に書くと、脚力があまりにも釣り合わない先生、生徒グループとは途中で別れ、私達は強力(=山岳ガイド)の世話になりながら、マイペースであえぎ登り、とうとう頂上を極めたのでした。私はひどい高山病にかかり、頭痛に泣きながらてっぺんの火口壁に立ったのを覚えています。でも、頂上で拝したご来光の素晴らしさは、生涯忘れられません。行きも帰りも六合目に一泊するという、超スローモー登山でした。
考えるに、富士に登るということは、実に様々な意味で、勉学や人生に似ているのです。
すなわち、裾野が長くて、見えている頂上が容易に近づきません。(基礎的な修練は、時間が長くかかりあきやすいのです)
頂上に近くなるほど、つらくなります。(ほんとうの実力や奥義、あるいは人間的深みには、なまやさしい努力では達し得ません)
登るには、自らの足を前にふみ出すしかありません。(全く同様で、これが校訓「勤勉」の精神)
それをたゆまず続ければ、人よりおくれても頂上に達し得ます。(これも同様。英語で”Better late than never”「遅くとも、しないよりまし」といいます)
汗と涙で頂上をきわめたものだけが、真のそう快感を味わいます(それが実力です)
克己心とのたたかいです。(これも全く同じ)
つらいが楽しくもあり、自信をつけてくれます。(そもそも勉学をつらい、楽しくないなどど思わぬことです)
『思い出すことなどー回想の前学園長・母 島田依史子』
平成3年8月30日第一刷発行
平成5年3月1日第ニ刷発行
著者:島田和幸
発行者:島田燁子
