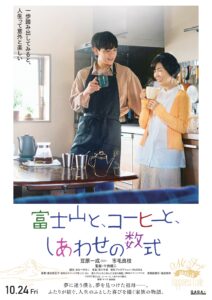
今回も、第2代理事長の島田和幸先生著『思い出すことなど』から、和幸先生が依史子先生がなぜ富士山をこよなく愛したかを記していますので、ご紹介します。
思い出すことなど 島田和幸
P.73 万里の道も一歩から 勉学や人生に似る富士登山 より抜粋
ところで、周知のように古来日本人は、富士をこよなく愛しました。「こんな立派な山はどこにもあるまい」と、きっとよその国のことなら知らなくとも思っていたのに違いありません。深い進行の対象でもありました。また、刻々と変容する富士の姿に、人間にも似た喜怒哀楽を感じとったかも知れません。昔から、富士がちょっとでも見えるところには、必ずといってよいほど「富士見町」や「富士見台」があるのを見ても、その親近感のほどがうかがわれます。
さて、創立者が富士をこれほどまでに愛した意義を考えてみると次の五つになると思います。
一、いつ(四季おりおりに)見ても美しい。
二、四方八方、どこから見ても美しい。
三、あらゆる人が見て、美しい。
四、みる人に、心の安らぎと勇気を与えてくれる
五、日本最高峰でありながら、来る者を拒まない。(誰でも登ろうと思えば、頂上に立つことが出来る。)
ます、一と二ですが、このふたつを人間の理想の姿と考えたのでしょう。裏表のない公正な人、努力をいとわなぬ人、姿勢のいい人、いつも泰然としている人、そのような人間の姿は、いつどこから見ても美しいのです。舞台俳優などは、背中で演技が出来れば一流、といわれるそうですし、また、子どもは親の背中(=黙々と苦労を重ねる親の姿、というほどの意味か)を見て育つ、とも言います。前は何とか格好がついても、後ろや横は難しいのです。
三と四は、清楚な美、永久不変の美、気高さ、包容力、安定感といったようなものでしょうか。
五は、これがすこぶる重要です。富士は三七七六メートルという一番高い山ですが、日本アルプス主峰のような、高度な熟練、装備、体力などを特に必要としません。必要なのは、登りたいという意志の発動と、途中であきらめない粘り強さです。裾野はきわめて長く、頂上に近づくほどにつらさがひどくなり、やめて下りようかという誘惑がおそいます。九合目あたりであきらめるひとは、かなりいます。一歩前進半歩後退とため息の連続で、克己心の自己テストのようです。
この続きは次号で。
『思い出すことなどー回想の前学園長・母 島田依史子』
平成3年8月30日第一刷発行
平成5年3月1日第ニ刷発行
著者:島田和幸
発行者:島田燁子
